分電盤や制御盤内で、安全な接地(アース)を確保するために使用されるのが「アース端子台」です。接地線の集約やメンテナンス性の向上を目的として使用され、機器の保護と電気設備の信頼性向上に貢献します。本記事では、アース端子台の構造・種類・実際の接続方法について詳しく解説します。
アース端子台の役割
- 複数の接地線を1点に集約し、確実なD種接地へ導く
- 接地線の保守点検・増設・交換を容易にする
- 盤内での接地回路を視覚的に整理し、安全性を確保
主な構造と種類
- ネジ式端子台:リングスリーブ端子や圧着端子をボルトで固定
- ばね式端子台:工具不要で線材を直接挿入でき、振動にも強い
- DINレール取付型:制御盤内で多用。他の端子台と一体化しやすい
- 導通バー付きタイプ:複数端子の導通を一括化。接地集約に便利
接続方法と配線のコツ
- 接地線は基本的に緑または緑/黄線を使用(JIS C 9330)
- 端子にはリング端子やY型端子を圧着して接続
- 電線サイズ(例:IV1.6mm²〜5.5mm²)に適合する端子台を選定
- ネジ部はトルク管理を行い、ゆるみ・緩みを防止
- 接地母線とボンディングする場合は、導通確認を必ず実施
設置例と運用上のポイント
- 分電盤内の左下など、配線しやすい位置に固定
- 端子台にラベル(例:E1、E2)を貼り、回路識別を明確に
- 複数系統を導入する場合、バー導通部と独立部の使い分けを行う
おすすめ製品
まとめ
アース端子台は、小さな部品ながら電気設備の信頼性・安全性を左右する重要な構成要素です。種類ごとの特徴を理解し、配線方法やトルク管理にも配慮することで、接地の品質を高め、設備全体の保守性向上につながります。

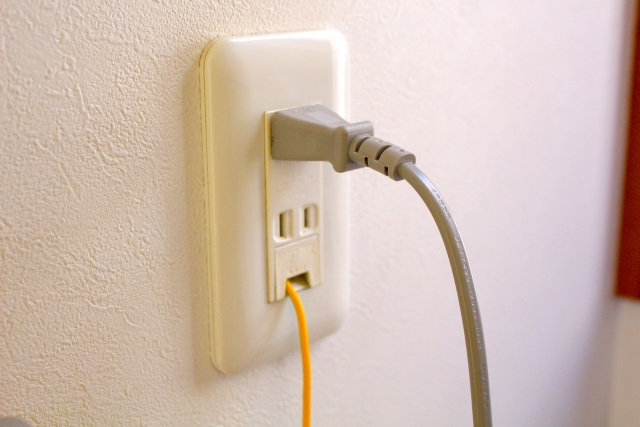


コメント